はじめに
クレステッドゲッコー(Correlophus ciliatus)は、「クレス」という愛称で親しまれているヤモリです。目の上から首にかけて生えているトゲトゲした飾り(クレスト)や、一匹ずつ異なる美しい体の色、そして比較的大人しい性格から、初めて爬虫類を飼う方にも人気があります。
もともとニューカレドニアという南の島に生息していますが、日本で生まれた個体(CB個体)が広く流通しており、以前よりも手に入れやすくなりました。このガイドでは、クレスが健康で長生きできるよう、飼育に必要な情報を全てご紹介します。
- クレステッドゲッコーってどんなヤモリ?
名前と見た目の特徴
クレステッドゲッコーという名前は、目の上から首にかけて生えている「クレスト」と呼ばれるトゲトゲした飾りに由来しています。体の色や模様は「モルフ」と呼ばれる多くの種類があり、個性豊かな見た目を楽しめます。大人になると、尻尾を含めて20~25cmほどの大きさになります。
どんな暮らしをしているの?
故郷であるニューカレドニアの森で、主に木の上で生活する「樹上性」のヤモリです。夜行性なので、昼間は木の葉の裏や木の隙間に隠れて静かに過ごします。性格はおとなしいですが、中には触られるのが苦手な子もいるため、その子の性格に合わせて接してあげましょう。
どれくらい生きるの?
飼育下での寿命は10年前後といわれています。適切な飼育環境を整え、バランスの取れた食事を与えることで、クレスは本来の寿命をまっとうできます。 - 快適なお家(ケージ)を準備しよう
ケージの選び方と置き場所
クレスは木の上で生活するヤモリなので、高さのあるケージが必須です。初めて飼う場合は、幅30cm × 奥行30cm × 高さ45cm程度のケージがおすすめです。脱走を防ぐためにフタはしっかり閉まるもの、そして十分な空気の通り道(通気性)があるものを選びましょう。
多頭飼育は、繁殖目的の場合を除きおすすめしません。ケンカやストレスの原因になるため、基本的に一匹ずつ飼育しましょう。
床材の選び方と管理
床材には、ヤシガラ土、キッチンペーパー、人工芝などがよく使われます。それぞれにメリット・デメリットがあるので、何を重視するか(清潔さ、湿度の保ちやすさ、見た目など)に合わせて選びましょう。
床材の種類 メリット デメリット
ヤシガラ土 自然な見た目でレイアウトが映える、湿度を保ちやすい うんちが見つけにくい、交換や掃除が少し大変
キッチンペーパー 衛生的で手入れが簡単、安価 見た目がシンプル、湿度を保ちにくい
人工芝 レイアウトが引き立つ、清潔で掃除がしやすい 最初に敷くのが少し手間がかかる
ヤシガラや土のような細かい床材を使う際は、誤ってクレスが食べてしまう誤飲に注意が必要です。床材はこまめに交換し、常に清潔に保ちましょう。
レイアウトを工夫しよう
クレスが立体的に動き回れるよう、ケージの中には木の枝、流木、コルクなどを配置しましょう。枝状のコルクを登り木として、筒状のコルクを隠れ家として使うのも効果的です。
また、夜行性のクレスが落ち着いて休めるよう、隠れ家(シェルター)を必ず用意してください。素焼きのウェットシェルターは、湿度を保てるだけでなく、クレスが水を飲む場所としても使えます。
フロッピーテール症候群を防ぐために
ケージのレイアウトが縦方向のものばかりだと、クレスが壁にばかり張り付いて休む癖がつき、尻尾の筋肉や骨が変形する「フロッピーテール」の原因になることがあります。これを防ぐため、流木を斜めに置いたり、水平な止まり木を増やすことが非常に重要です。 温度・湿度・照明をしっかり管理しよう
ちょうど良い温度設定
昼間は24~28℃、夜間は17~24℃が適温とされています。多くの飼育情報では、25~27℃がちょうど良い温度だといわれています。
特に夏場は、30℃を超えると突然死する危険があるため、ケージ内の温度が高くなりすぎないよう注意が必要です。冬場は、ケージの壁にパネルヒーターを貼るなどして暖めてあげましょう。保温球を使う際は、火傷を防ぐために必ずケージの外から使用してください。
湿度管理は徹底的に!
適切な湿度は60~80%が目安です。湿度が低いと、脱皮がうまくいかない「脱皮不全」の原因になります。
乾湿のサイクルを意識しよう
クレスの自然な環境では、雨が降って湿度が高くなった後、徐々に乾燥するという「乾湿のサイクル」があります。これを再現するために、1日1~2回、朝晩に霧吹きで湿度を上げましょう。霧吹きの量は、次の日の朝にはケージの中が乾いているくらいが目安です。常に湿った状態だと、カビや細菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。
照明は必要?
クレスは夜行性なので、基本的な飼育では紫外線ライトは必須ではありません。しかし、健康維持のために弱い紫外線ライトを当てることも効果的です。設置する場合は、光から逃げられるシェルターを必ず用意しましょう。
ケージは、昼夜の明るさの違いがわかる場所に置き、直射日光が当たらない場所に置いてください。 毎日のお食事と栄養
クレステッドゲッコーは何を食べるの?
クレスは昆虫や果物、花の蜜などを食べる雑食性です。最近では、昆虫を与えなくても飼育できる「完全栄養食」の人工飼料が主流になっています。
主食の選び方
人工飼料の種類とあげ方
クレス専用の人工飼料は、水で溶いてペースト状にして与えます。さまざまな味があるので、飽きさせないように複数のフードを交代で与えるのがおすすめです。ご飯のお皿に盛り、次の日の朝には食べ残しを片付けましょう。
昆虫食のあげ方と注意点
人工飼料だけでも飼育は可能ですが、コオロギなどの昆虫を副食として与えるのも良いでしょう。昆虫を与える際は、必ずケージ内に残さないようにしてください。食べ残したコオロギはクレスを噛んで怪我をさせる可能性があります。また、野外で捕まえた虫は、寄生虫などの危険があるため絶対に与えてはいけません。
サプリメントは大切?
昆虫や果物をあげる場合は、カルシウム剤をまぶすことが必須です。カルシウムが不足すると、骨に異常が出る「クル病」の原因になります。カルシウムの吸収を助けるビタミンD3入りのサプリメントも、週1~2回程度与えると良いでしょう。
ご飯をあげる頻度
成長段階によって調整します。赤ちゃんのうちは毎日少しずつ、大人になったら2~3日に1回程度の頻度で与えましょう。 健康管理とよくある困ったこと
病気やトラブルに早く気づくためには、毎日の観察が何よりも大切です。以下のチェック項目を参考に、クレスの様子をよく見てあげましょう。
チェック項目 内容
— —
食欲 ご飯をしっかり食べているか、食べ残しが増えていないか
うんち 色や形、量がいつも通りか、下痢や血が混じっていないか
動き 夜になると元気に動き回っているか
皮膚・目 古い皮が残っていないか、目やにや目の乾燥はないか
よくある健康問題- 脱皮不全: 指先や目の周りに古い皮が残っている状態。湿度が足りないことが主な原因なので、霧吹きの回数を見直しましょう。
- フロッピーテール: 尻尾の付け根が垂れ下がるように曲がる症状。水平な止まり木を増やすことで予防できます。
- 食欲不振: 餌を口にしない、食べる量が減る。温度や湿度の乱れ、ストレス、脱皮前の反応などが原因と考えられます。まず飼育環境を見直し、改善しない場合は動物病院へ相談しましょう。
- 自切(尻尾を切ってしまうこと): 驚いた時やストレスを感じた時の防御反応。一度切れた尻尾は再生しません。出血はほとんどないので、ケージ内を清潔に保ち、傷口がふさがるまでそっとしておけば問題ありません。
- クレステッドゲッコーとの触れ合い方
ハンドリングの基本と注意点
クレスは人に慣れることもありますが、ハンドリングはクレスにとってストレスになる可能性もあります。無理に触りすぎず、少しずつ慣れさせていくのが良いでしょう。
ハンドリングで最も大切な注意点は、尻尾を持って持ち上げないことです。尻尾は非常にデリケートで、不適切な扱いをすると自切してしまう可能性があります。また、一度切れた尻尾は再生しないことを覚えておきましょう。
ストレスを与えないための気配り
クレスにストレスを与えないためには、静かで落ち着いた環境を心がけましょう。掃除やレイアウトの変更、ハンドリングを行う際は、急な動きや大きな音を避け、丁寧に行うことが大切です。
おわりに
クレステッドゲッコーは、その魅力的な容姿と比較的飼いやすい性質から、素晴らしいパートナーになってくれるでしょう。このガイドで紹介した飼育方法や健康管理のポイントを実践することで、クレスはより長く、健康に暮らすことができます。
彼らは言葉を話せないので、毎日の観察が何よりも大切です。小さな変化に気づくことが、病気の早期発見につながります。もし飼育中に困ったことや不安なことがあれば、一人で抱え込まず、爬虫類を診てくれる動物病院に相談してください。適切なサポートを得ることで、クレスとの生活はより楽しく、充実したものになるはずです。

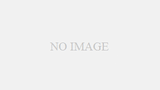

コメント